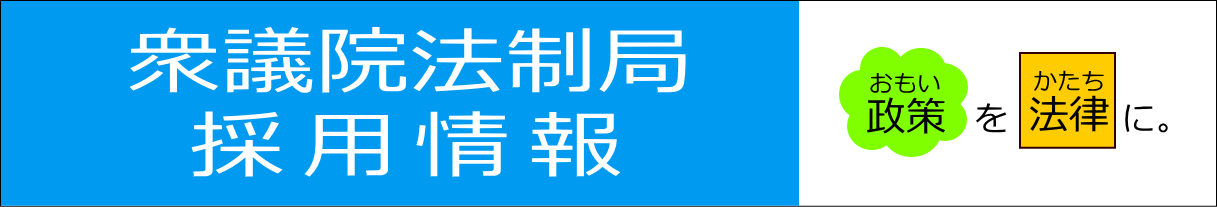- メインへスキップ
- 音声読み上げ

- サイト内検索
過去の出題例
| 試験年度 | 憲法 | 行政法 | 民法 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 |
PDF(試験問題) [52KB] PDF(参照条文集) [192KB] HTML |
PDF(試験問題) [92KB] PDF(参照条文集) [352KB] HTML |
PDF(試験問題) [80KB] PDF(参照条文集) [916KB] HTML |
| 令和5年度 |
PDF(試験問題) [68KB] PDF(参照条文集) [192KB] HTML |
PDF(試験問題) [68KB] PDF(参照条文集) [156KB] HTML |
PDF(試験問題) [60KB] PDF(参照条文集) [916KB] HTML |
| 令和4年度 |
PDF(試験問題) [96KB] PDF(参照条文集) [228KB] HTML |
PDF(試験問題) [36KB] HTML |
PDF(試験問題) [64KB] PDF(参照条文集) [760KB] HTML |
令和6年度
憲法
以下の学生A及びBの会話を読んで、問に答えなさい。
学生A「近いうちに衆議院が解散されそうだね。昨日のニュースで解説していたけど、まだ野党の選挙体制が整っていないらしく、今選挙すれば与党が大勝するかもしれないみたいだよ。」
学生B「前から気になっていたんだけど、衆議院の解散って政府与党に相当有利な仕組みだよね。自分たちに最も有利なタイミングで選挙をすることができるんだから。そんな不公平な制度は問題だと思うな。」
学生A「そういえば、昨日のニュースで、X党の甲議員が衆議院の解散を制限する法律案を検討していると言っていたよ。でも、内閣に自由な解散権があるとすると、その行使を制限する法律はおよそ憲法違反になるんじゃないかな。」
学生B「内閣に自由な解散権があるっていうけど、そもそも、憲法上の根拠はどこにあるんだろう。」
学生A「確か、憲法7条の『内閣の助言と承認』が根拠だったよね。」
学生B「でも憲法4条によると、天皇には国政に関する権能がないんだよね。天皇は形式的・儀礼的な国事行為しかできないはずで、『内閣の助言と承認』もそれに対するものに過ぎないんじゃないかな。 それに、憲法7条が根拠だとして、本当に自由な解散権があるといえるのかな。」
〔問〕
(1) 解散権の所在とその行使が認められる場面について、論点を整理した上で説明しなさい。
(2) 甲は、衆議院の解散を制限する法律案の内容として、①衆議院の解散事由を限定することを考えており、それが難しい場合には、②解散前に衆議院でその解散理由について議論するための手続を創設することを考えている。上記下線部①及び②を法制化しようとする場合の憲法上の論点について、解散制度の持つ意義を踏まえつつ、あなたの考えを述べなさい。なお、その際、考えられる法制度設計について言及することを妨げない。
参照条文
日本国憲法【略】
行政法
次の会話は、衆議院法制局での上司Aと部下Bが、新たな立法に取り組むに当たり、ブレインストーミングをしているときのやりとりである。部下Bの空欄①~④にふさわしい行政法上の論点を論じなさい(※会話文は「です・ます」調で掲載されているが、解答に当たっては、「です・ます」調で表記しても、「だ・である」調で表記しても、採点には影響しない。)。
A:どのような行政分野の法律の立法に当たっても、法律において行政処分の要件を書き切ることは難しいので、一定程度、行政庁の裁量を認めるものになることはしばしばありますよね。法の要件について行政裁量が認められる場面において、その判断が後に司法で争われることとなったとき、行政処分の違法性はどのような基準で判断されていますか。あるいは、そうした一般論を定立することは難しいですか。
B:①
A:そうですね。ここで留意したいのは、行政庁の専門的・技術的判断が必要である場合においても、行政裁量が認められるかどうかは、個別の行政法分野の行政目的や、行政処分の性質、専門的・技術的判断に至る手続などによって、変わりうるということです。例えば、原子力発電所(原子炉)の設置許可と公害患者に対する給付認定を比較すると、いずれも専門的・技術的判断が必要であるものの、考慮すべき事情には違いがあると思いますが、具体的にはどのような違いがありますか。今、私は2つの分野の例を挙げましたが、他の例を挙げても構いません。
B:②
A:少し観点が変わる問題となりますが、産業廃棄物処理施設の設置許可などでは、周辺住民が反対運動を起こしたりすることなどから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の要件を満たしていても、行政庁が周辺住民の同意を取り付けることを産業廃棄物処理業者に求めることがあるようです。法律に根拠がないものの、行政庁としては、産業廃棄物処理業者が円満に事業を進められるよう、独自の指導要綱などを制定して、これに基づき周辺住民の同意の取付けを求め続ける一方、産業廃棄物処理業者がこれを顧みることなく、あくまで廃棄物の処理及び清掃に関する法律の要件を満たしているとして申請をした場合について、この申請に対する不許可処分は許されますか。
B:③
A:以上を踏まえた上で、立法のお手伝いをするに当たっては、行政庁の裁量を事前に統制するなどして紛争を防ぎながら、事後に紛争になってしまった場合に救済手段が確保されていることが重要ですね。例えば、産業廃棄物処理施設の設置許可申請に対する不許可処分の判断過程において、考慮すべきでないことを考慮した違法があった場合、産業廃棄物処理業者としては、どのような手段により司法救済を求めることが考えられますか。
B:④
参照条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第一条、第十四条第五項第二号イからヘまで、第十五条の二【略】
行政事件訴訟法 【略】
行政手続法 【略】
民法
次の文章を読んで、後記の〔問1〕、〔問2〕及び〔問3〕に答えなさい。
[事実Ⅰ]
1.A及びBは、「こしひかり」を生産する米農家であり、隣人同士である。
2.令和6年初頭のある日、A及びBの住む地域を大きな地震が襲った。Aは、外に出て、自宅に特段の損傷がないことを確認したが、その際、隣接するB所有の古い米蔵が大きく損傷し、A宅の方に傾いていることを発見した。Aは、急いでこのことをBに知らせようとしたが、連絡が付かず、Bが年末から海外旅行中であることを思い出した。
3.余震の発生も予想される中、(ア)Aは、「Bが大切にしていた米蔵が崩れでもしたら大変だ、また、そうなれば隣接する我が家にも被害が及びかねない」と考え、自己の名義で米蔵の修理をC工務店に依頼した。米蔵には必要最低限の応急的な修理が施され、AはCに修理費用10万円を支払った。
4.その後、Bが海外旅行から帰宅した。
〔問1〕
[事実Ⅰ]を前提として、次の問いに答えなさい。
Aは、Bに対し、米蔵の修理費用10万円の支払を請求することができるか。下線部(ア)の事実がどのような法律上の意義を有するかに言及しつつ、論じなさい。
[事実Ⅱ](事実Ⅰの続き)
5.Bの米蔵は、本格的な修繕が行われることになり、当分の間使用ができない状態となった。この状況を心配したAは、Bに、大型の低温貯蔵庫を所有するDを紹介することにした。Dは、元々Aが、無償で、その収穫した「こしひかり」100㎏を保管してもらっている者であった。
6.交渉の結果、Bも、その収穫した「こしひかり」200㎏を、無償で、Dの貯蔵庫で保管してもらえることになった。なお、Dは、貯蔵庫内にある大型の容器に、Aの「こしひかり」100㎏を保管していたが、A及びBの承諾を得て、当該容器にBの「こしひかり」200㎏も混合して保管することにした(A及びBの「こしひかり」は同一種類・同一品質であり、10㎏当たり5,000円相当である。)。
7.ところが、DがAの「こしひかり」に加えてBの「こしひかり」も保管するようになってからしばらくしたある日、Dの貯蔵庫に何者かが侵入し、容器に保管されていた「こしひかり」60㎏が盗取された。なお、何者かに貯蔵庫への侵入を許したのは、その日はDが貯蔵庫の施錠を忘れていたためである。また、貯蔵庫に侵入した者は不明であり、盗品を取り戻すことは不可能である。
〔問2〕
[事実Ⅰ]及び[事実Ⅱ]を前提として、次の問いに答えなさい。
この時点で、A及びBは、Dに対し、契約に基づき、それぞれ何㎏の「こしひかり」の返還請求権を有しているか。
また、A及びBは、Dに対し、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができるか。
[事実Ⅲ](事実Ⅰ・Ⅱの続き)
8.盗難事件を知り、Dの保管態勢に不信の念を抱いたBは、「Aへの返還分が足りなくなってしまうだろうが、今のうちにDから返せるだけ返してもらい、全て売却してしまおう」と考え、Dに対し、契約に基づくものとして、「こしひかり」200㎏の返還を求めた。Dは、あまり深く考えることなくこの求めに応じ、Bに「こしひかり」200㎏を返還した。
9.Bは、Dから返還を受けた「こしひかり」200㎏について、直ちに、以上の経緯を何も知らないEに、代金20万円で売却した。Bは、Eから代金全額の支払を受けるとともに、Eに「こしひかり」200㎏を現実に引き渡した。なお、当該「こしひかり」200㎏は、本来であれば10万円相当であるところ、20万円という高値で売却することができたのは、Bの特別な才覚によるものであった。
10.その後、AがDに対し「こしひかり」100㎏の返還を求めたところ、Dは以上の経緯により貯蔵庫内には「こしひかり」40㎏しか残っていないとして、Aに「こしひかり」40㎏を返還した。
11.Aは、「(イ)BがDから返還を受け、Eに売却した『こしひかり』200㎏のうちの一部は、そもそも自分のものであったのだから、その現物の返還か、それに代わる金銭の支払を請求したい」と思っている。
〔問3〕
[事実Ⅰ]、[事実Ⅱ]及び[事実Ⅲ]を前提として、次の問いに答えなさい。
Aの下線部(イ)の主張の根拠を明らかにし、その主張の当否を検討した上で、Aが、誰にどのような請求をすることができるか、論じなさい。
参照条文
民法 第一編~第三編【略】
令和5年度
憲法
以下のA及びBの学生の会話を読んで、問に答えなさい。
学生A「最近、いわゆる『宗教二世』に関する報道が多いね。」
学生B「そうね。『宗教二世』の中には、親が信仰している宗教の教義を自分の子に対して教育し、その教団や親から、やりたいことを制限された、と言っている人が多いのよ。」
学生A「例えば、どんなことが制限されたの?」
学生B「ある宗教団体の信者は、その教義に基づき、『宗教二世』である中学生や高校生に対し、格技の授業では実技に参加せずに見学するよう指導していたのよ。『宗教二世』である中学生や高校生は『格技の授業で実技に参加したら、地獄に落ちるから絶対やめなさい』などと言われ、逆らえない状況になっていたようよ。」
学生A「実技に参加しないと、卒業が危ういんじゃないの?」
学生B「卒業だけなら、レポート提出等の代替措置で何とかなったみたいね。ただ、『宗教二世』の中には、真摯な信条に基づいて格技の実技に参加しなかった者もいたけど、実技に参加している同級生をうらやましく思いながら見学していた者もいたそうなのよ。」
学生A「それはかわいそうだね。何とかならないのかな?例えば、18歳未満の者は心身が未発達であることも考慮して、⑴①何人も、18歳未満の者に対し、不当にその意思を拘束するような方法で、宗教上の教義の教育を行ってはならないこととし、この規定に違反した場合には必要な改善命令を行った上で、それでも改善が見られない場合には処罰することで、防止することはできないかな?」
学生B「行政庁は、違反状況に関する情報収集を、どのような方法で行うことを考えているの?」
学生A「⑴②行政庁が立入調査をすることを考えているよ。ただ、さすがに立入調査の相手方の抵抗を排してまで立入調査を行うのはやり過ぎだと思うから、立入調査を拒否した者を処罰することにとどめる方がいいんじゃないかな。」
学生B「うーん、憲法上大丈夫かしら。憲法と宗教というと、そういえば、最高裁判所の判例では、政教分離関係のものをよく目にするわね。」
学生A「政治と宗教団体って、そもそも関わっていいのかな。信者から集めたお金を原資として、政治家に対して寄附をすることで政治に対する一定の影響力を持つのは、良くないんじゃないかな。⑵宗教団体については、政治活動に関する寄附全般を禁止することも必要だと思うよ。」
学生B「現行法でも、会社や労働組合などの団体は、政治活動に関する寄附について、政党及び政党のために資金を援助することを目的とする政治資金団体に対するものに限って認められているわね。宗教団体には、これよりも規制を強化するってことなの?」
学生A「うん、そうだよ。」
学生B「宗教団体の信者からの寄附が原資だと、少なくとも表面上は、宗教団体と構成員との間の衝突は、ないようにも思えるけど・・・」
〔問〕
Aが提案している傍線部⑴の①及び②並びに⑵の方策を法制化しようとする場合における憲法上の問題点について、論じなさい。
参照条文
日本国憲法【略】
行政法
事例1
2020年夏、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第38条第1項に規定する「特定都道府県知事(※)」であるAは、キャバクラやホストクラブなどの接待を伴う飲食店が新型コロナウイルス感染症の感染拡大の根源となっていると考え、県内のこれらの施設に対し、特措法第45条第2項を根拠として21時以降の営業を停止するよう要請した。
しかし、接待を伴う飲食店の多くは、その外観からでは閉店しているか否かの確認が困難であったところ、当時の特措法には、各施設での感染防止策の実施状況を確認するための調査権限が定められていなかったこともあり、任意調査によって区域内の接待を伴う飲食店が要請に応じているか否かを確認することは困難を極めた。
このような状況に対し、Aは、要請に応じているか否かを確認するため、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第37条第2項による立入権限を利用し、警察職員に県職員が同行する形で、県内の接待を伴う飲食店に立入検査を行うこととした。
その結果、キャバクラBについて、21時以降も営業を続けていることが発覚したことから、AはBに対し、特措法第45条第3項の規定による指示及び同条第4項の規定による公表を行うことを考えている。
事例2
同じく特定都道府県知事であるCは、飲酒を伴う会食が新型コロナウイルス感染症の感染拡大の要因であると考え、接待を伴う飲食店を含む県内の全ての飲食店に対し、特措法第45条第2項を根拠として、酒類の提供を取りやめるよう要請した。
この県では、かねてより、キャバクラやホストクラブなどの接待を伴う飲食店に対し、法令の遵守状況を確認するための定期的な立入検査が行われていた。
県の警察職員は、Cが酒類の提供を取りやめる旨を要請した時期においても、定期検査の一環として、キャバクラ、ホストクラブへの立入検査を行っていたが、その際、たまたま、ホストクラブDにおいてシャンパンコール(シャンパンの注文が入ったテーブルに店の従業員が集まって行われるパフォーマンスのこと)が行われているのを目撃した。シャンパンコールの中で読み上げられた飲料の名前から、ホストクラブDにおいてシャンパンが提供されていると考えた警察職員は、この事実を県職員に伝えた。
特措法には各施設での感染防止策の実施状況を確認するための調査権限が定められていなかったこともあり、追加調査は難しいと考えたCは、警察職員から提供された情報を根拠に、Dに対して、特措法第45条第3項の規定による指示及び同条第4項の規定による公表を行うことを考えている。
(※)特措法の「特定都道府県知事」…特措法32条1項の規定により「新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域」としての指定を受けた市区町村が属する都道府県の知事のこと。
〔問1〕
事例1、事例2における行政法上の論点について、それぞれ説明しなさい。
〔問2〕
議員Xは、キャバクラやホストクラブに対する立入検査そのものは必要であったものの、風営法を根拠としたことには問題があると考えている。
そこで、衆議院法制局の職員Yに対し、特措法第45条第2項の要請に応じ、又は同条第3項の指示に従っているかを確認するための調査権限を、新たに特措法に設けることができないかと相談した。YがXに確認したところによると、調査権限の内容としては、風営法第37条第2項と同じようなものを考えているとのことである。
当時の特措法の規定を前提とした場合、Yは、Xに対しどのような助言を行うことが考えられるか。
参照条文
新型インフルエンザ等対策特別措置法 第一条、第三十二条、第三十八条第一項、第四十五条【略】
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第十一条、第十二条【略】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第一条、第二条第一項、第三十七条第二項~第四項、第五十三条【略】
民法
以下の[事実関係]を前提に、〔問1〕及び〔問2〕に答えなさい。
[事実関係Ⅰ]
① Xは、飲食店に経営の診断や助言を行うコンサルタントである。
② Xは、令和5年7月1日、カフェを営むYとの間で、メニュー開発や店舗運営等に関する助言を主な業務として、コンサルティング契約を締結した。契約期間は同日から3年間とし、Xの報酬は月額10万円で、毎月その翌月末日までに支払うこととした。
なお、契約期間の途中での契約解消については合意がなかった。
③ Xの助言が功を奏し、Yのカフェは人気店となった。しかし、Yは次第にXの助言を軽視し、報酬の支払を渋るようになった。
④ Yは、令和7年6月分の支払を最後に、それ以降の報酬を支払わなくなった。その後も、Xは、Yを説得しつつ、適切な助言を続けていたが、Yは、令和8年3月1日にXとの契約を解消する旨の通知を送付し、同日Xに到達した。
〔問1〕
Yが主張する契約の解消は認められるか。また、Xは、Yに対し、どのような請求を行うことが考えられるか。それぞれ検討しなさい。
[事実関係Ⅱ](事実関係Ⅰの続き)
⑤ Xは、Yと連絡が取れなくなったため、自己の金銭債権を行使する前提でYの財産を調査したところ、次のような事実が判明した。
・Yは、令和7年6月1日、Z社に対し、令和9年5月31日を返済期日として、300万円を貸し付けていた。
・Z社は、Yと以前から取引のある厨房機器の販売業者である。
・Yには、Z社への貸金債権以外にめぼしい財産がない。
⑥ そこで、Xは、令和9年7月1日、Z社に対し、Yからの借入れについて問い合わせたところ、次のような事実が判明した。
・Z社は、令和4年4月7日に、Yに対し、厨房機器を代金500万円で販売し、同月8日に引き渡した。代金の支払期日は、同月15日と定められていた。
・厨房機器の引渡し以降、YとZ社との間で、催告等を含め、代金債権に関するやりとりはなく、Yからの支払も一切なかった。
・Z社は、令和9年6月25日に、厨房機器の代金債権の存在を思い出し、Yに対する300万円の借金と相殺しようと考えている。
⑦ Xは、Z社のYに対する代金債権が既に時効にかかっているのではないかと考えている。
〔問2〕
Xは、令和9年7月1日現在において、Yに対する金銭債権の回収を図るため、Z社に対し、どのような請求・主張を行うことが考えられるか。事実⑦記載のXの見立てを踏まえながら、Z社からの反論も想定しつつ、Xの請求が認められるか否かを検討しなさい。
参照条文
民法 第一編~第三編【略】
令和4年度
憲法
以下のA、B、C3人の学生の会話を読んで、問に答えなさい。
[学生の会話]
女子学生A「母が、『新型コロナウイルス感染症のワクチンを打つと不妊になるから、打たないで』って言うのよ。」
男子学生B「それって、厚生労働省が否定しているよね。」
女子学生A「そのことも伝えたのだけど、『信頼できる医師がSNS上で言っている』の一点張りなのよ。そもそも、科学的な根拠のない発言は、多くの人を惑わし、その健康をも脅かすおそれがあるのだから、何らかの規制が必要だと思うの。例えば、SNS事業者に対して、そのSNSに書き込まれている、科学的な根拠もなく『新型コロナウイルス感染症やワクチンに関する政府の見解』を否定する虚偽の発言を削除する義務を課すというのはどうかしら。」
男子学生B「確かに、SNS上には荒唐無稽な発言もあるとは思うけど、いろいろと考えなければならない点が多そうだね。それより、SNS上の発言と言えば、他者に対する侮辱的な発言の方が目に余るよ。健康を脅かすどころか、命を落とすことさえあるのだから、SNS事業者に対して、利用者の申告に応じて、一定の期間内に『他者に対する侮辱的な発言』を削除する義務を課すべきだと思うね。」
男子学生C「ちょっと待って。2人の言っていることは、結局のところ憲法問題になるのではないかな。それより、SNS事業者に対して、『利用者が実名を明らかにしなければ発言できないような仕組み』を設けることを義務付けるべきだよ。そうすれば、2人が言っているような問題も自然と解決するよ。」
〔問〕
A、B、Cの3人が提案している方策(下線部)を法制化しようとする場合における憲法上の問題点について、異なる立場から表明されると考えられる意見にも言及しつつ、自由に論じなさい。なお、憲法上の論点に付随して、その政策としての合理性の問題に言及することを妨げない。
参照条文
日本国憲法【略】
行政法
経済対策として、売上が前年度に比べて50%以上減少した事業者に対する給付金の給付事業が実施された。この給付金を受給するための要件や手続は、この給付金を所管する省庁の長が定めた「給付金交付規程」により定められている。なお、この給付事業は法律の根拠なく行われた。
〔問1〕
この給付事業を法律の根拠なく行うことについて、行政法の基本原理に照らして問題となりえる点について、複数の立場からの見解を紹介しつつ、説明しなさい。
〔問2〕
給付金交付規程に、「この給付金を不正に受給した事業者は、その名称を公表される」旨の定めがあるとした場合、どのような行政法上の問題があるか。説明しなさい。
民法
Ⅹは、令和4年5月1日に開催予定の1万人規模の野外音楽イベント(以下「本件イベント」という。)に参加したいと思い、これを主催するイベント企画会社Yのウェブサイトで、本件イベントのチケットを購入し、その代金1万円を支払った。その際、Xは、画面上に「チケット販売規約」へのリンクが表示されていることを気にも留めないまま、「チケット販売規約に同意する」のチェック欄にチェックを入れた上で、チケットの購入に進んでいた。
Xは、本件イベントを心待ちにしていたが、折しも、令和3年の年末から、感染力の非常に強い新型感染症が全国的に大流行するに至り、令和4年2月には、大規模イベントの中止を指示することができる新法が制定、施行された(なお、中止指示の違反について、特段の罰則は定められていなかった。)。同年4月1日、政府は、この新法に基づき、Yに対し、本件イベントの中止を指示した。翌2日、Yは、当該指示に従い、やむなく本件イベントの中止を決定した。
以上の事実を前提として、次の問1に答えなさい。
〔問1〕
Xは、Yに対し、本件イベントのチケット代金の払戻しを求めることができるか。チケット販売規約に①何ら払戻しに関する規定がなかった場合と、②「不可抗力によるイベント中止の場合には、チケット代金の払戻しは行わない」との規定があった場合とに分けて、答えなさい。なお、複数の法律構成が考えられる場合は、それぞれについて検討しなさい。(ただし、消費者契約法については検討しなくてよい。)
上記の事実に加え、以下の事実があった。
Yは、本件イベントの準備段階において、本件イベントの参加者に配布するためのオリジナルデザインのピンバッジ(以下「本件ピンバッジ」という。)の製作・供給を業者Zに発注していた。その契約では、Zが自己の材料を用いて本件ピンバッジ1万個を製作した上で、これを令和4年4月10日にZの自社倉庫で引き渡すこと、同月20日にYがZに代金300万円を支払うことなどが合意されていた。
Zは、契約どおり、本件ピンバッジ1万個を製作した上で、同月10日、自社倉庫でこれを引き渡せるように準備をして待っていたが、Yは引き取りに来なかった。ZがYに連絡して引取りを求めたところ、Yは、「イベント中止により本件ピンバッジも不要になった。不可抗力であるから引き取る必要はないし、代金も支払えない」と主張し、取り合わなかった。
以上の事実を前提として、次の問2に答えなさい。
〔問2〕
同月15日の時点で、Zは、Yとの契約を解除し、Yに対して損害賠償を請求することができるか。
参照条文
民法 第一編~第三編【略】