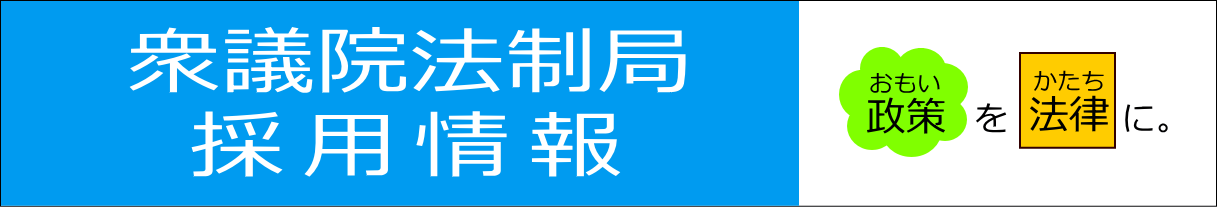- ���C���փX�L�b�v
- �����ǂݏグ

- �T�C�g������
�L�����A�`��
�u�q��Ē��̐l�ɔz������E��ł��v
�O�c�@�@���ǂł́A�d���Ɖƒ�̗����x�����x�̊��p���i���͂��߁A���[�N�E���C�t�E�o�����X�ɔz�������������̎����ɐϋɓI�Ɏ��g��ł��܂��B�q��Ē��̐E���ɁA���ۂɗ��p�������x��A�d���Ǝq��Ă̗������ɂ��ĕ����Ă݂܂����B
���Ă��ꂽ�l

�q��ĂƎd���̗����ɓ�����A�ǂ̂悤�Ȑ��x�𗘗p�����H
���ɂ͂R�l�̎q�ǂ������܂����A���̈玙�̂��߁A�j���E�����g���鐧�x�͂قڑS�ė��p���Ă��܂����B
�܂��A�o�Y�̍ۂɂ́A�u�z��ҏo�Y�x�Ɂv�i���P�j�y�сu�玙�Q���̂��߂̋x�Ɂv�i���Q�j���擾���܂����B�q�ǂ������̐V�������ɂ́A���ꂼ��Q�������x�́u�玙�x�Ɓv���擾���܂����B�玙�x�Ƃ���̕��A��́u�玙���ԁv�i���R�j�𗘗p���āA�Ζ����Ԃ�Z�k���Ă��܂����B
���݂́A�u���o�x�o�Ζ��v�i���S�j�Ɓu�x�e���Ԃ̒Z�k�v�i���T�j�𗘗p���Ă���A�Ζ����Ԃ͑��̐E���Ɠ����ł����A�q�ǂ����������w�Z��ۈ牀�ɑ���o������A�����x�߂ɏo���Ă��܂��B
�i���P�j�z��҂̏o�Y�ɔ������@���̕t�Y�������s���ꍇ�̋x�Ɂi�Q���ԁj
�i���Q�j�z��҂̎Y�O�Y����Ԓ��ɏo�Y�ɌW��q����{�炷�邽�߂̋x�Ɂi�T���ԁj
�i���R�j�q��{�炷�邽�߂P���̋Ζ����Ԃ̈ꕔ���Ζ����Ȃ����Ƃ�F�߂鐧�x
�i���S�j�q�̑��}���̂��ߎn�ƁE�I�Ǝ�����ύX���邱�Ƃ��ł��鐧�x
�i���T�j�x�e���Ԃ��P���Ԃ���30���ɒZ�k���邱�Ƃ��ł��鐧�x
�ƒ�ł͂ǂ̂悤�ȉƎ��E�玙��S�����Ă���H
�Ǝ��E�玙�̗D�揇�ʂɂ��Ă̔F����v�w�ŋ��L������ŁA���m�ȕ��S�͌��߂��ɏɉ����ĕK�v�Ȃ��Ƃ�����Ă��܂��B
��ɂ���Ă���Ǝ��E�玙�́A�Ǝ����Ɨ��������A�玙���Ə��w�Z�E�ۈ牀�ւ̑���o���A�H���̕⏕�A�����C���X�ł��傤���B�ŋ߂͎q�ǂ��������傫���Ȃ��Ă����̂ŁA�ꏏ�ɃT�b�J�[�̗��K��������{�[�h�Q�[���������肵�Ă��܂��B
�q��ĂƎd���̗����ɓ�����A�S�|���Ă��邱�Ƃ́H
�E��ɉƒ�̎����`���Ĕz�����Ă��炤�ƂƂ��ɁA�Ƒ��ɂ��d���̏�`���ċA��x���Ȃ邱�Ƃւ̗��������Ă��炦��悤�ɓw�߂Ă��܂��B
���N�́A���ۂ̖@�Ă��T�{��������ȂǁA���ɑ��Z�ȋƖ��ł������A�j���[�X�ŒS�������@�Ă̂��Ƃ����ꂽ�ۂɁu��������͂��̖@������邨��`�������Ă����v�Ɛ���������A�q�ǂ�������E�ꌩ�w�i���U�j�ɘA��Ă����肵�āA�d���ւ̗�������������悤�ɐS�����Ă��܂��B
�i���U�j�ċx�݂̎����ɍs����A�E���̉Ƒ����E���̎���������K���O�c�@�@���ǂ̎�g
�@���ǂ͎q��Ē��̐E���ɔz�����Ă����E��H
�O�c�@�@���ǂ́A�E���̐������Ȃ��A�u��̌�����E��v�ł��̂ŁA�q��Ē��ł��邱�ƂɌ��炸�A���ꂼ��̌ʂ̎���ɂ�������ƌ��������A�z�����Ă��炦�Ă���Ɗ����Ă��܂��B
�E��̏�i�⓯���ɔ��ɏ������Ă���Ƃ�������������̂ŁA�����g���A�����̎q��Ă���i��������A�������玙�x�Ƃ�Ζ����Ԃ̒Z�k�����擾���₷���悤�Ȋ��ɂ��Ă��������Ǝv���Ă��܂��I
�u�F�X�Ȑ��x���g���čœK��WLB��͍����Ă��܂��v
�O�c�@�@���ǂł́A�d���Ɖƒ�̗����x�����x�̊��p���i���͂��߁A���[�N�E���C�t�E�o�����X�ɔz�������������̎����ɐϋɓI�Ɏ��g��ł��܂��B�q��Ē��̐E���ɁA���ۂɗ��p�������x��A�d���Ǝq��Ă̗������ɂ��ĕ����Ă݂܂����B
���Ă��ꂽ�l

�q��ĂƎd���̗����ɓ�����A�ǂ̂悤�Ȑ��x�𗘗p�����H
�O�c�@�@���ǂł́u�Y�O�E�Y��x�Ɂv�ɉ����A�q�ǂ����R�ɂȂ�܂Łu�玙�x�Ɓv���擾�ł��A���̊��Ԃ͎����őI�����邱�Ƃ��ł��܂��B���́i�d���̓s���ł͂Ȃ��j������ۊ��̓s���ő傢�ɔY���A�Y�x�E��x���킹�Ĕ��N�ł̐E�ꕜ�A�����߂܂����B
�t���^�C���Ζ��ł̕��A�ɓ������ẮA�܂��O�̎q�ǂ��Ɖ߂������Ԃ���������m�ۂł���悤�A�u�t���b�N�X�Ζ��v�i���j�Ɓu�玙���ԁv���̏����x���t�����p���A�����I�ɂ͏T�x�R�����Ƃ���X�^�C�����Ƃ�܂����B
����ɁA�T�P���́u�ݑ�Ζ��v�Ƃ��邱�ƂŁA�o���T�R���ɍi�邱�Ƃ��ł��A�̗͖ʂłƂĂ����肪���������ł��B
��i�A�����̗����̂��ƁA�P�̈Č����ۂ̑S���ŒS������`�[�����̐E�ꂾ���炱���ł������������Ǝv���܂��B
�i���j�S�T�ԒP�ʂőS�̂̋Ζ����Ԑ���ς��邱�ƂȂ��A�Ζ����ԑт𑁂߁i�x�点�j����A�P���̋Ζ����Ԃ�Z���i�����j�����邱�Ƃ��ł��鐧�x�B�玙��쓙�̎������E���́A����ɉ����A�T�x����y���ɉ����P���݂��邱�Ƃ��ł���B �Ȃ��A�T�x���̒lj��̐��x�ɂ��ẮA�s���E�̍��ƌ������Ɠ��l�ɁA�ߘa�V�N�S���P���ȍ~�A�玙��쓙�̎���Ȃ���ʂ̐E���ɂ��K�p���g�傳���\��B
���݂̋Ɩ����e�⓭�����́H
�o�Y�O�Ɠ������A�c�����@�̗��ē��̋Ɩ��ɏ]�����Ă���A���݂͌o�ώY�ƁA���A���q�͕����S�����Ă��܂��B
�E�ꕜ�A����Q�N�ȏ���o�āA�u�t���b�N�X�Ζ��v��u�ݑ�Ζ��v�̐��x�̗��p�͑������A�œK�ȃ��[�N���C�t�o�����X��͍�������X�ł��B�Ⴆ�A����J��̔ɖZ���ɂ͌����o���A���ɋƖ������č���ł�����͉Ƒ��ƒ������Ďc�Ƃ��s������A��͏o�Γ������炵���肵�Ă��܂��B
�ٓ��O�̕����i�_�ѐ��Y����S���j�ł́A�_���̌��@�Ƃ�����H���E�_�ƁE�_����{�@���S�����I�Ԃ�ɉ�������t�@�ɑ��āA�S�{�̏C���Ă����s�ŗ��Ă��܂����B��o���O�͂Ă�����ł������A�_�Ƃ̂�����ɂ��Ă̍���ł̋c�_��[�߁A�n�c�̏�ő��������s���Ƃ����A�c������`�̖{���I�ȃv���Z�X���x����d�����ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�l�I�ɂ��A���̊��Ԃ͈玙���Ƒ��ɔC���A�v���Ԃ�ɐ��ʂ���v�����藧�ĂɎ��g�ނ��Ƃ��ł��A��ςȂ�����[���������Ԃł����B
���̗͂����Ƌ��͂����Ă̂��Ƃł����A���ꂩ����A�q��ĂƎd���̗�����}��Ȃ���A�q�ǂ��ƈꏏ�ɐ������Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
�u���w�o���Łu�����o���v��������I�v
�O�c�@�@���ǂł́A���E���ɑ��č����O�̑�w�@���ւ̗��w��ʂ��A���x�Ő��I�Ȓm����g�ɕt��������Ă��܂��B���w�o���̂���E���ɁA���w���x�◯�w��ł̌o�����ɂ��ĕ����Ă݂܂����B
���Ă��ꂽ�l

�ǂ��ɗ��w���A���w��łǂ̂悤�Ȍo���������H
���́A�A�����J�̃��[�X�N�[���ɂQ�N�ԗ��w���܂����B�P�N�ڂ̓j���[���[�N�ɂ���R�����r�A���[�X�N�[���̏C�m�ے��ŃA�����J�̊�{�I�Ȗ@���L���w�т܂����B�Q�N�ڂ̓��T���[���X�ɂ���UCLA���[�X�N�[���̏C�m�ے��ŃA�����J�̊��@�ƐŖ@���U���܂����B
�A�����J�̃��[�X�N�[���ł́A���@�̃[�~������@�̃N���j�b�N�Ō��n�w���Ƌc�_�����킷�����āA�č��@�̌n�ւ̗�����[�߂܂����B�܂��A�w���c�̂̃{�����e�B�A������w����������ʂ��āA�@���x�̔w�i�ɂ��镶����K����̌�����@��邱�Ƃ��ł��܂����B
��]����A�N�ł����w�ɍs�����Ƃ��ł���H
�O�c�@�@���ǂł́A�C�O�̑�w�@�ւ̗��w���x���݂����Ă���A���N�P���͗��w�ɍs���Ă��܂��B��N�̗̍p�l��������ł��邱�Ƃ��l����ƁA�{�l����]����A���w�̋@��͑傢�ɊJ����Ă���Ƃ����܂��B���w��Ƃ��ẮA�������w�����A�����J�̃��[�X�N�[���̂ق��A�C�M���X�̑�w�@�Ő����w�����������U����E����������ۂ�����܂��B�܂��A�t�����X�̑�w�@�ɗ��w�����E�������܂����B
���w�܂łɁA��w���C�Ȃǂ̃T�|�[�g�͂���H
��w���C�ɂ��ẮA�O�c�@�����ǂ̂��̂ɎQ���ł��܂��B��̓I�ɂ́A��b���x���̌��C���牞�p���x���̌��C�܂ŁA�X�l�̌�w���x���ɉ��������C����u�ł��鐧�x�������Ă��܂��B
�܂��A�ے����͂��ߓ����ۂ̕��X�����w�������C�ɂ����Ă�����������A���w�o���̂���E��������ʂ���ʂɂ��ėl�X�ȃA�h�o�C�X�������������肵�܂����B
���w�������Ƃ��A�d���ɐ����Ă���H�i�������Ă��������H�j
���w�o���́A����̖@���ǂł̎d���ɐ����Ă���ƍl���Ă��܂��B
�c������̗��Ĉ˗��ɂ́A���O���̖@���x�ɒ��z�����̂����Ȃ�����܂���B�Ⴆ�A���W�܂̗L�����������������ɁA�v���X�`�b�N���݂̖�肪���ڂ��ꂽ�ۂɂ́A�A�����J��EU�̋K���ׂĂق����Ƃ̈˗�������܂����B�A�����J���w�ɂ���āA���̂悤�Ȉ˗��ɍőP��s�������߂́u�����o���v�𑝂₷���Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
My career story �T�i�����܂ł̃L�����A�`���j
�O�c�@�@���ǂł́A���̍�����@�������d���Ɋւ��@���������܂��B����ɁA���Ă̌o���܂����C�O�Ƃ̌𗬓��A�@���Â��肩��h���������l�Ȍo�����҂��Ă��܂��B�����ł́A���݁A�@�Ă̐R���Ɩ���C�O�ڋ�����S�����Ă���E���ɁA����܂ł̌o����A�d���̂�肪�����ɂ��ĕ����Ă݂܂����B
���Ă��ꂽ�l

- Profile
- 2017�N�@���ǁ@����ہi�������Z�E�\�Z�j
- 2017�N�@��O�����ہi�O���E�����Ȋw�E�Ȋw�Z�p�j
- 2019�N�@�@����撲������{�@���ہi���@�E�I�����j
- 2021�N�@�@����撲������撲���ہi�c�^���j
- 2022�N�@�@����K��
- 2023�N�@�@�ĐR�����R�����ہ@�i���E�j
�O�c�@�@���ǂ��u�]�������R�́H
�w������ɖ@�����w�сA�@���̒m��������悤�Ȏd�����������ƍl���Ă����ۂɁA�O�c�@�@���ǂ̑��݂�m��܂����B�����̑�\�ł��鍑��c���̗��@�������T�|�[�g���A�Љ���̉�����}��Ƃ������ł͂ł��Ȃ��d�����e�ɊS�����ƂƂ��ɁA�Q�E�R�N�����Ɍo������ٓ���ʂ��ĂP�{13�Ȓ��ɂ܂����镝�L������Ɍg��邱�Ƃ��ł���_�ɂ��傫�Ȗ��͂������܂����B
�@���ǂ͂ǂ̂悤�ȐE��H
���ǑO�́A�P�����Z�@�Ƃɂ�߂��������Ȃ����Ƃ�����C���[�W������Ă��܂������A���ǂ���ƁA�c���̐搶���Ƃ̑ō����⍑��R�c�̃T�|�[�g���͂��߂Ƃ���u�O�ɏo��d���v���������ƂɋC���t���܂����B�c���̐搶���ƂƂ��ɖ@���Ă̒��g�����グ�Ă����ߒ���A�@���Ă����ۂɍ���ŐR�c�����ߒ��������̖ڂŌ��邱�Ƃ��ł���Ƃ���ɁA���̎d���̖ʔ������肪��������Ǝv���܂��B
�܂��A���̂�������l�X�Ȏd����C���Ă��炦��E��ł�����A�P�N�ڂ̂�������@���Ă̌��Ă̍쐬�Ɍg��邱�Ƃ��ł������Ƃ��ƂĂ���ۂɎc���Ă��܂��B
����܂łɂǂ̂悤�Ȗ@���̗��ĂɌg����Ă����H
���́A����܂łɂR�̉ۂŖ@���Ă̗��ĂɌg���܂����B
�ꕔ�ł͂���܂����A��ȈČ��Ƃ��āA�P�ڂ̉ۂł͊w�Z����ɂ�����ICT�̊��p�𐄐i���邽�߂́u�w�Z�������i�@�v�̐���Ⓦ���I�����s�b�N�̊J��̓����ɍ��킹�ĂR�̏j�����ړ������邱�Ɠ�����e�Ƃ���u���O�r�[W�t���[�@�E�I���p�����[�@�v�̉����ɁA�Q�ڂ̉ۂł͐V�^�R���i�E�C���X�����ǂւ̜늳���ɂ��O�o���l�̑ΏۂƂȂ�A�I���ɍs�����Ƃ��ł��Ȃ����ɓ��[�@����m�ۂ��邽�߂́u�R���i���ғ���X�֓����[�@�v�̐���ɁA�R�ڂ̉ۂł͍���c���Ɏx������鋌���ʔ�̓����x�����߂邽�߂́u�Δ�@�v�̉����Ɍg���܂����B
�ٓ����o������x�ɑS���قȂ镪��̖@���Ă̗��ĂɌg��邱�Ƃ��ł��A���ɕ��ɂȂ�Ɗ����Ă��܂��B
���Ɉ�ۂɎc���Ă���Ɩ��́H
�ǂ̈Č�����ۂɎc���Ă��܂����A���Ɉ�ۂɎc���Ă���̂́u���{�ꋳ�琄�i�@�v�̐���Ɍg��������Ƃł��B���̖@���́A���{�ɋ��Z����O���l�̕��ɑ�����{�ꋳ��𐄐i���邽�߂ɁA��{���O����{�ꋳ��̐��i�Ɋւ���{��̊�{�ƂȂ鎖�����߂�A������u���O�@�v�������̂ł����A���̖@�����ł������Ƃ܂��A���{�ɂ���āA���{�ꋳ��@�ւ̔F�萧�x����n�݂��邽�߂̖@��������܂����B�c�����@����̓I�Ȑ��{�̎{��ɂȂ���������Ƃ��āA���Ɉ�ۂɎc���Ă��܂��B
���Ă̎Q�l�Ƃ��āA���ۂɓ��{�ꋳ����s���Ă���w�Z�Ɏ��@�ɍs�������Ƃ��A�v���o�[���ł��B
���E�����猩���@���ǂ̓����₷���́H
�O�c�@�@���ǂ́A�l�������Ȃ��E��ł��镪�A�E�����m�̋������߂��A���������Ƃ╪����Ȃ����Ƃ�����Ε����̊_�����z���đ��k�ł���悤�Ȋ��������Ă���A���ɓ����₷���E�ꂾ�Ǝv���܂��B�܂��A����̊J��͋Ɩ����Z�����Ȃ邱�Ƃ�����܂����A��͔�r�I���������Ă��邽�߁A�d���A��ɏK�����ɒʂ����Ƃ��ł��A�v���C�x�[�g�Ǝd���̗����Ƃ����ʂ���������₷���������Ă��܂��B
�d���������ŐS�|���Ă��邱�Ƃ́H
���R�̂��Ƃł͂���܂����A�P�P�̈Č��ɐ����Ɏ��g�ނ��Ƃł��B�O�c�@�@���ǂ́A�^��}���킸�A�S�Ă̋c���̐搶�����T�|�[�g����g�D�ł���A�ǂ̗���ɂ����Y�����Ƃ����߂��܂��B�������_�ɂ��ĕ����̉�h����˗����邱�Ƃ�����A�u���̉�h�̗���Ȃ�ǂ̂悤�ɍl���邩�v����Ɉӎ����Ȃ��痧�Ă��邱�Ƃ����߂��܂��B�ǂ̉�h�̐搶��������M�����Ă���������悤�A�S�Ă̈Č��ɑS�͂Ŏ��g�ނ��Ƃ��d�v���ƍl���Ă��܂��B
My career story �U�i�Ǘ��E�܂ł̃L�����A�`���j
�O�c�@�@���ǂł́A�@���Ǔ��ŗl�X�ȕ���̖@���Ɍg���Ȃ���A�܂��A�C�O���w�o����o���o�����ς݂Ȃ���A�L�����A�A�b�v��}���Ă����܂��B�����ł́A���݊Ǘ��E�ɂ���E���ɁA����܂ł̌o����d���̂�肪�����ɂ��ĕ����Ă݂܂����B
���Ă��ꂽ�l

- Profile
- 2000�N�@���ǁ@��ꕔ���ہi���t���j
- 2002�N�@��ܕ����ہi�J���j
- 2005�N�@�������w�@������w�@��w�iGRIPS�j
- 2006�N�@�@����撲������{�@���ہi���@�E�I�����j
- 2009�N�@�C�O���w�@�p�E�u���X�g����w
- 2011�N�@��x�擾�i�P��ځj
- 2012�N�@�@���劲�t
- 2013�N�@��x�擾�i�Q��ځj
- 2015�N�@����ہi�@���j
- 2016�N�@�o���@���@�R�������
- 2018�N�@��l�����ے��i�_���j
- 2021�N�@��ܕ����ے��i�J���j
- 2023�N�@��ꕔ���ے��i�����j�i���E�j
�Q�O�O�O�|�Q�O�O�S ���� ���t�A���S�ۏ�A�J���S��
�O�c�@�@���ǂɓ��nj�ŏ��ɔz�����ꂽ�̂́A���t�E���S�ۏᓙ��S�������ꕔ���ۂł����B���߂Ĕz�����ꂽ���A�ۂł͊��������ĂɊԈႢ���Ȃ����𐺂ɏo���ēǂ݂Ȃ���m�F����u�ǂݍ��킹�v�ƌĂ���Ƃ����Ă���Ƃ���ŁA�u�Ӗ���������Ȃ��Ǝv������Ǖ����Ă��Ă��������v�ƌ����A�����ɂ͕����R���Ǝ����R���A���X���ɂ͋ǒ��R�����A�����ɂ͈ψ���̎��^���ψ���Ŋԋ߂Ɍ��A�@�Ă̐����ɗ�������ƂƂȂ�܂����B��ςȂƂ���ɗ��Ă��܂����A�Ƃ����v��������܂������A��y�����ƂĂ��D�������J�ɋ����Ă��ꂽ�̂ŁA���߂Ă̌o���̘A���ɕs�����o���邱�Ƃ͂���܂���ł����B
���̌�A����@�l�̉��v��l������̐��i�A�j���@�̉����Ȃǂɂ��Ă̗��Ă�S�����A�o����ςݎn�߂Ă���2�N�ځA9.11�̃e�����N����܂����B���{�����o���ꂽ�e�������[�@�ɑ��ė^��}�o������C�����c�Ɍ��������k������܂������A�̌��̑O���̐[��ɗ^��}���c������A�^�}�Ɩ�}���ꂼ�ꂪ�C���Ă��o���邱�ƂƂȂ�܂����B�O��̗��ĂƂȂ��āA�������̋ǒ��ɋǒ��R�������肢���A�邪�����Ă����̂��ǒ����Ō��Ȃ���A���E��̕ω��⍑����̏d�v�ۑ�ɑΉ����邽�߂ɍ��̗��@�̍őO���Ŏd�������Ă��邱�Ƃ��������܂����B
���̗��N�ɂ͌����E�J���E���̒S���Ɉٓ����A�k���N�f�v��Q�҂̋A�����āA�f�v��Q�Ҏx���@�𗧈Ă��邱�ƂƂȂ�A���̎v�����������܂����B
�Q�O�O�T �������w
2005�N�ɂ͍������w�̋@��^�����A������w�@��w�Œm�I���Y����@���ɂ��ĂP�N�ԕ����܂����B���߂Ă��������������@��Ƃ��Ă��M�d�ł������A���Ԋ�Ƃ�S���̒n�������c�̂���h�����ꂽ������������A���E�e������̗��w�������Ƃ̌𗬂����Ɋy�����A������L���邱�Ƃ��ł��܂����B
�Q�O�O�U�|�Q�O�O�W ���@�E�I�����S��
���{�����@�̐��肩��60�N�̐ߖڂɂ́A���@�����������[�@�̗��ĂɌg��邱�ƂɂȂ�܂����B
���̉ߒ��ł́A�����Ɏ^���̐��}���甽�̐��}�܂ŁA�S�Ẳ�h���Q�����Ę_�_�������d�˂��܂����B����܂��āA�^�}�Ɩ���}�����ꂼ��@���Ă𗧈Ă��Ē�o���A����ɂ��̖@���Ăɂ��ăe�[�}�ʂ̏��ψ����݂���ȂǏ[�������ψ���R�����s���܂����B����ł̋c�_�̌��ʁA�^�}�Ɩ���}�����݊��A���ꂼ��C���ėv�j�\���A����ɋ��c���������܂����B�ŏI�I�ɂ͗^�}�Ɩ���}����v���邱�Ƃ͂Ȃ��A�^�}�̕����C���ĂƖ���}�̏C���Ă����ꂼ���o����A�^�}�̕����C���Ă�������邱�ƂƂȂ����̂ł����A�c���ԂŐ^���ɋc�_��[�߁A��v�ł���_�Ƃǂ����Ă���v�ł��Ȃ��_�����o���Ă����P�N�ȏ�ɋy�ԋ��c���x���A�^�}�āA����}�āA���ꂼ�ꂩ���o���ꂽ�C���Ă̑S�Ă𗧈Ă��邱�Ƃ��ł��A���@�[�~�o�g�̎��ɂƂ��āA�ł��Y����Ȃ����ĂƂȂ�܂����B
�Q�O�O�X �p�����w
�O�c�@�@���ǂł͊C�O���w����]����l�ɐϋɓI�ɗ��w�����߂Ă���A����10�N�ڂɃC�M���X�ɗ��w����@��邱�Ƃ��ł��܂����B���ۊC�m�@�═�͕����@�AEU�@�A�C�M���X���@�ȂǁA����܂ł̐l���ōł����������P�N�ԂƂȂ�܂����B���S�ۏ��S�����Ă����Ƃ�����C�ɂȂ��Ă����C�m�@�═�͕����@�ɂ��Ă̍��ۃ��[�����w�Ԃ��Ƃ��ł������ƁA���{�Ƃ͑S���قȂ�EU�Ƃ����X�̎匠���Ƃ����g�g�݂��ǂ̂悤�ɓ����Ă���̂���m�邱�Ƃ��ł������ƁA�P��̐������@�T���Ȃ��C�M���X�ɂ����錛�@�̎d�g�݂����߂Č������邱�Ƃ��ł������ƂȂǁA������̂����ɑ傫���[���������w�����ł����B
�Q�O�P�P�\�Q�O�P�Q ��x�擾��A�@���劲�t��
���w����A����A��x�ڂ̑�ꕔ���ۂ��o�āA���q���o�Y�B�q���P�ɂȂ�܂ň玙�x�Ƃ��擾���܂����B
�玙�x�Ƃ���̕��A��́A�@���劲�t�ƂȂ�A�Ǔ����C��C�O����̌��C���̎����A�@�������̌����Ȃǂ�S�����܂����B���̂Ƃ���悵���Ǔ����C�́A�V�l��n�������c�̂���̌��C���Ȃǂ�Ώۂɂ����@�������ɂ��Ă̖{�i�I���̌n�I�ȋǓ����C�Ƃ��č��ɑ����Ă��܂��B�܂��A�C�O�̗l�X�ȍ����猤�C��������A���{�ɂ����闧�@�ߒ���c�����@�̌���A�@���x�v�̕��@�A�����ɑI�ꂽ�c���Ƃ����⍲����c�@�@���ǂ̂��ꂼ��̖����Ƌ����݂̍���Ȃǂ�`����o���́A����܂ł̖@���ǂł̌o����U��Ԃ�A���߂Ď���̎d���̂���ׂ��p�ɂ��čl����悢�@��ƂȂ�܂����B
�Q�O�P�R �Q��ڂ̈�x�擾
���q�ƂQ�ΈႢ�ő��q���o�Y���A�Q��ڂ̈玙�x�Ƃ��擾���܂����B���܂ꂽ����̎q�̐��b�����ł͂Ȃ��A���t��b���n�߂���̎q�Ƃ�����������������āA�Ƒ��Ƃ̎��Ԃ��߂������Ƃ��ł��܂����B
�Q�O�P�T �@���S��
2��ڂ̈玙�x�Ƃ��畜�A���āA����ۂŖ@���̒S���ƂȂ�܂����B���ǂ���15�N���o�����̍��ɂ́A�ے���⍲���ċc���Ƃ̑ō������c�ɓ��s����ق��A�@���āE�C���Ă̗��Ă̒��j�ƂȂ�A�W�Ȓ��Ƃ̒����Ȃǂ��s���Ă��܂����B
�����A���t����Y���i�ז@�������āi�撲�ׂ̘^���E�^��A���Ӑ��x�A�ʐM�T��̊g�哙�j����o����A���̗^��}�C�����c�ɉے��ƂƂ��ɗ�������ƂƂȂ�܂����B�@���Ȃ�������ĘA���C�����c���s���A�Ō�ɂ͗^��}�̋c���݂̂ŁA�̌��O���̖�܂ł��肬��̌��������܂����B�C�����c�������ꍇ�ɔ�������}�Ă��p�ӂ��Ă����̂ł����A�Ō�ɂ͗^��}�ʼn��Ƃ����ӂɎ���܂����B�ق��Ƃ��܂������A�����ɗ����̐R�c�Ɍ������C���Ă̗��Ă�Ǔ��R���A�ψ���ł̎��^�Ή��ɒǂ��邱�ƂɂȂ�܂����B
�܂��A�ĔƖh�~���i�@�̗��ĂɌg��邱�Ƃ��ł������Ƃ��悢�v���o�ł��B
�Q�O�P�U�|�Q�O�P�V ���@�R������ǂɏo��
���@�����������[�@�̗��Ă���10�N��B���@�ɂ���č���ɐݒu���ꂽ���@�R����̉^�c�E��������S���O�c�@���@�R������ǂɏo�����邱�ƂɂȂ褌��@�Ɋւ��钲����S�����܂����B
���@�R������ǂł́A���@�R����ɂ�����c�_��[�߂邽�߁A���O�ɐR����ŋc�_�����e�[�}�Ɋւ��钲���������쐬���A�R������o�[�ɔz�t���Ă��܂��B�����������쐬����Ƃ��́A�c���̖��ӎ��܂��A�ŐV�̊w���┻��A�C�O�ɂ����铮���ׁA�c���ɕ�����₷���`����ɂ͂ǂ�����悢�����l���܂��B���̂ق��A�R����ōs��ꂽ�c�_��v�Ď��m������A�C�O�̌��@����̒��������܂Ƃ߂���A�e���}�ɂ�����c�_��⍲���邽�߂Ɏ������쐬���Đ��}�̉�c�ɏo�Ȃ����肵�Ă��܂����B
����̌��@�_�c���x���钲���́A���̏�ł̕��ƈႢ�A�ӔC�d��ł����A�쐬������������ɋc���Ԃŋc�_���[�߂��Ă����̂����̏�Ō��邱�Ƃ��ł����т�����܂����B
�Q�O�P�W�| �_�ѐ��Y�A�J���A�����S��
�Q�N�Ԃ̎����ǂւ̏o���̌�A�Ǘ��E�Ƃ��Ė@���ǂɖ߂�܂����B���̌ケ��܂łɁA�ݕ������ԉ^�����Ɩ@�����A�H�i���X�팸���i�@�A�I�c�n��U���@�A�ƒ{�`���a�\�h�@�����A�{�ؔ_�ƐU���@�����A�h�Џd�_�_�Ɨp���ߒr�h�ЍH�������i���[�@�A�J���ҋ����g���@�����A�ΖȌ��N��Q�~�ϖ@�����A�e�틋�t���̍����֎~�@�Ȃǂ̗��Ă�S�����A�����͂�������S���v�Ő������܂����B
�ƒ{�`���a�\�h�@�����́A���O���Ŋg��𑱂���A�t���J�ؔM�����{�ł����������ꍇ�ɔ����āA���{��o�̖@�Ă��������{�s�����܂łً̋}�̑[�u�Ƃ��āA�\�h�I�E�������\�ɂ�����̂ł������A�ꍏ�������@���x���������Ȃ���ΊԂɍ���Ȃ��Ƃ����c���̋ٔ������v�����A�N���N�n�ԏ�ŗ��Ăɓ�����܂����B
�c���Ƃ̑ō����ȂǂŒ��S�ƂȂ��ē����͉̂ے����̊Ǘ��E�ł��B�c���Ƃ̐M���W��z���Ȃ���A�ō������d�˂Ė@���Ă̓��e���ł߂Ă�����Ƃ́A�m�I�Ȗ`���ł��B�ꂵ���ʂ�����܂����A��肪��������A�y�����[�����������ł��B�܂��A�Ǘ��E�Ƃ��āA�ۈ������N�Ɋy����������悤�ɉۓ����}�l�W�����g���邱�Ƃ��ے��̖����ł��B�ۈ��̊F���ǂ̂悤�ɐ������Ă������������ꏏ�ɍl���A���̐������ԋ߂Ɍ��邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��A���X�̊�тł��B
����܂ł̃L�����A��U��Ԃ���
2000�N�̓��Ljȗ��A���̂ق��ɂ��A�����琄�i�@�A�J����@�C���A��Q�Ҋ�{�@�����A���E�I���@�����A���������K���@�����A��Q�b�^�̉���Q�ҋ~�ϖ@�ȂǁA�l�X�ȕ���̗��ĂɌg���A�C�O���w��o���ȂǁA�@���ǂ̊O�ł��o����ς�ł��܂����B
�O�c�@�@���ǂł́A���ǒ��ォ��ۂ̋c�_�◧�č�Ƃɉ���邱�ƂɂȂ�܂��B�ۂł̋c�_�́A���ǔN���Ƃ͊W�Ȃ��A���ꂼ��̈ӌ����Ԃ������A���悢�@���x�Ƃ���ɂ͂ǂ�������悢�̂����l���܂��B���̒��̕ω��ɑΉ����邽�߂ɗ��@����ۂɂ́A�w����ߋ��̔���ׂĂ������������邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A�����̖@���x���Q�l�ɂ��A�c���Ƃ̂��Ƃ�܂��A�c�_���J��Ԃ��ĐV�����d�g�݂��l���Ă����K�v������̂ł��B�@���ǂŁA���邢�͖@���ǂ̊O�ŁA���l�Ȍo����ς݂Ȃ��琬�����A�������\�͂ƒm���̑S�Ă��A���̎d���ɐ����Ă����܂��B
�i���j�E���̏����́A���M�����i�ߘa6�N12���j�̂��̂ł��B