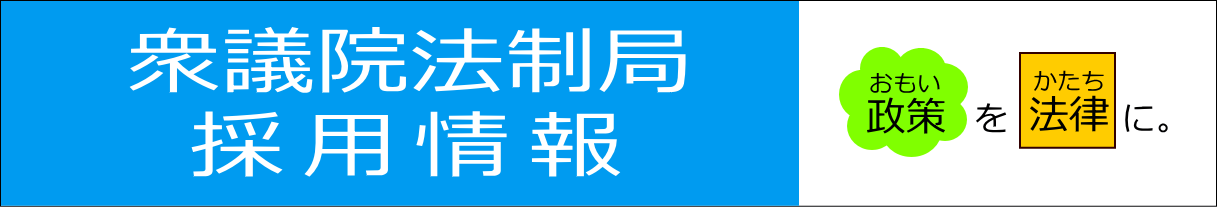- メインへスキップ
- 音声読み上げ

- サイト内検索
衆議院法制局長からのメッセージ
人間に対する温かい「まなざし」(令和7年)

今、世の中が、もの凄い勢いで変わりつつあります。私たちを取り巻く日常の世界、社会や経済も、絶えず変化しています。政治の世界、法律の世界も、決して例外ではありません。そうした時代の変化に取り残されることなく、生成AIなどを用いて臨機応変に対応していくことは、とても大事なことです。
その一方で、変わらないもの、決して忘れてはならないこともあります。それは、人間に対する「まなざし」です。私たちは、血のかよった生身の人間の営みと向き合って仕事をしているということです。
皆さん、「人間臭い」という言葉を聞いたことがあるでしょう。人間は、機械でもコンピュータでもありません。明らかに損な行為、明らかに不合理な行為と分かっていても、そういう選択をしてしまう。でも、それが人間なのであり、それに対しては、生身の人間が対応するしかないのです。
変化への冷静な対応と、「人間臭い」ものに対する温かい「まなざし」――そんな両面を持ち合わせた若い人たちと一緒に仕事ができるのを楽しみにしています。
衆議院法制局長 笠井 真一